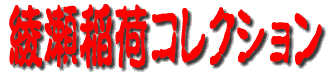
第4回地口行灯〜動物編〜
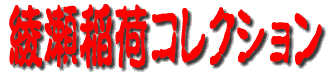
| 【これがオリジナル注文地口行灯】 実はこの円丈似顔絵の地口行灯、綾瀬稲荷の唐松宮司さんが。北千住の吉田絵馬屋さん(足立区千住4丁目)に頼んで特注したもの。唐松さんに感謝、感謝!「三河の太夫」と「みかんの太夫」を引っ掛けたもの。 なんで三河なんだ?と言えば円丈は愛知県出身で「三河」にしたようなんだ。ホント名古屋だから尾張なんだけど。まあ、細かいことはこっちに置こう。「みかんの太夫」は未完成な芸人と言う意味で「みかん」なのか?なんなのか?うん。今度聞いて見よう。 三遊亭 円丈 【製作 足立区千住4丁目 吉田絵馬屋】 ◎地口行灯〜狐編〜はこちら |
 |
| 【そもそも地口行灯とは?】 「地口行灯」とはなにか?まず地口は語呂合わせのことで。昔からのことわざや、誰でも知っているフレーズなどを語呂合わせのパロディにした絵紙。それを行灯の枠に貼ったものです。地口絵紙は江戸時代後期に生まれたものだといわれています。 |
| 〜動物編〜 地口行灯コレクション2 |
 |
【絵柄】 熊が振り分け荷物で箱根八里を越えてる絵柄 【意味】 書いてあるの文字は「箱根八里王(は)熊でも古す可゛」で元は「箱根八里は馬でも越すが」の地口になってる。 なお「箱根八里は馬でも越すが・・」あと「越すに越されぬ大井川」と続く訳。昔、東海道大井川の川越の大変さを表わした言葉なんだね。 |
【絵柄】 |
 |
|
|
【猩々とは?】 赤い長い髪を持ち、酒好きの水の妖精だと言う今で言う妖怪の一種? 【絵柄】 猩々が船を操って船頭の真似をしてる。 【意味】 ここには「せん登゛う」と書いてあり、「猩々せんどう(船頭)」。・・で元の言葉は何?それなんだ。元は「僧正遍照(そうじょう へんじょう)」でそれを引ッ掛けて「猩々せんどう(船頭)」となる。う〜〜ん、今の時代にはやや分かり難い。 |
【絵柄】 とんびが、畑に種を蒔いている。 【意味】 書いてある文字は「登んび可゛種まく」(とんびが種まく)で元は「権兵衛が種まく」、良く「権兵衛が種まきゃ、カラスがほじくる」と言うあれが元になっている。これも30代以下では分かりにくい言葉になりつつあるのだろうか?やや淋しいねえ。 |
|

|
【絵柄】 馬が五郎時至致(ときむね)になっている。えっ、絵の説明になっていない?そう? 【意味】 「馬の五郎時致」と言うのは、「曽我の五郎時致(ときむね)」のシャレ。鎌倉時代の曽我兄弟仇討ちをした弟の方。兄は祐成、富士野の狩場で父の仇、工藤祐経を討った故事から来ている。 |
| もっと地口行灯を知りたい人は |
| 種類と分布 | 足立区立郷土博物館の美人で評判の学芸員、荻原ちとせ(おぎはら)さん の調査では絵柄は狐柄のみならず、絵馬屋で165種が確認されており、 清瀬市や長野県の小布施町などにも様々あるとか、また 「地口どうろう」などの別称もあるとのこと。 |
| 内 容 | 歌舞伎や謡の有名な言葉やことわざ・成語をもじっていうしゃれであって、この語呂合わせは、噺家に通じるものです。 地口行灯は浅草の伝法院通りにも掲げられていますし、年初め歌舞伎座では、歌舞伎の地口が販売されています。 |
| 連絡先 | 足立区立郷土博物館 大谷田5−20−1 月曜休館日 TEL3620−9393 テレホンサービス3620−9292 |
・・・・てなことで今回はコレまで!!
◎地口行灯〜狐編〜はこちら
◎綾瀬稲荷コレクション1に戻る
◎綾瀬稲荷TOPに戻る
◎狛研TOPに戻る
◎落語TOPに戻る