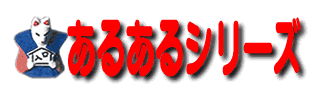
更新日05/11/15
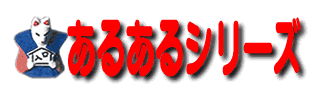 |
| その12:こんなにあるあるお能の伝習段階 |
お能には、入門したばかりの人から人間国宝の能役者まで多岐に渡る演者がいる。舞う演目は自分から選べる訳ではなく、修行を重ねていく中で、指導者に認められ、初めて演じることが出来るといわれる。
今回は、そんなあるある話をご披露します。 現行曲約200といわれていますが、長い修練を積む中で初めて習得を許される演目があることは、よく知られています。特に最奥曲は、三老女物として、「姨(伯母)捨」「関寺小町」「檜垣」の三曲は特に有名です。気合をいれて拝見すべきものですが、見慣れていないと見事に熟睡できるので、不眠症の方にはある意味お薦めとなります。失敬。 【また、その三老女については舞手の心境として知られている事では?】 ◎ 「姨(伯母)捨」は、寂しく感じるように舞う。 ◎「関寺小町」は老いた小野小町でも華やかさを感じられるように舞う。 ◎「檜垣」は朗々と舞う。と云われているそうです。 これは、見る側の心得とすべき所を示す為にも、この様な極意ともいうべき事が、敢えて一般にも知られているのだと思います。狂言役者の芸道修行では、ウツボ猿に始まり、釣狐で納めると言います。御能では、修練を積んで更に積んで習得を許されるもの(伝習)の段階があります。今回は観世流現行207曲を網羅したあるある。(唐松) |
|---|
こんなにあるあるお能の伝習段階 |
|---|
習物(ならいもの 5~1級) |
5級(36曲) |
|---|---|
4級(28曲) |
|
3級(49曲) |
|
2級(26曲) |
|
1級(33曲) |
|
準九番習(じゅん きゅうばん ならい) |
9曲 |
九番習 |
9曲 |
重習初伝(おもならい しょでん) |
4曲 |
重習中伝 |
4曲 |
重習奥伝 |
3曲 |
重習別伝(三老女はここ) |
4曲 |
| 神社界にも諸伝法があります。伝えられる処の大別方法は |
|---|
初 伝 |
|---|
中 伝 |
別 伝 |
奥 伝 |
奥 々 伝 |
極奥伝(ごくおくでん) |
秘 伝 |
口 伝 (簡潔にして重秘) |
◎しかし、まあ、落語家は前座、二ツ目、真打しかないのに随分あるもんですなあ・・(円丈)
| その11・ユネスコ世界無形遺産宣言「能楽」記念!! こんなにあるある花が出てくるお能の演目 |
 |
今回はユネスコ第一回世界無形遺産宣言「能楽」を記念しての特別企画。 お能には、花の精がシテとなって出てきたり、花を手に持ったり、冠に挿したり、作り物として飾られたりする。 今回はそんなあるある話でフラワー能!! 【 「半蔀(はじとみ)」立花供養。大阪能楽会館のチラシより転用】 |
| 花 の 種 類 | 御 能 |
| 松 | 高砂、老松、羽衣 |
| 竹笹 | 鳥追船、竹雪 |
| 笹枝(狂笹) | 隅田川、柏崎、百万 |
| 笹竹に文 | 花がたみ、高野物狂 |
| 梅 | 梅、箙、胡蝶、難波 |
| 若葉 | 求塚(芽吹いた薬草が若葉) |
| 桜 | 墨染桜、吉野天人、志賀、小塩 |
| 桃 | 西王母、東方朔 |
| 藤 | 藤 |
| 蕨 | 大原御幸 |
| 葵 | 加茂物狂 |
| 杜若 | 杜若 |
| 芍薬 | 養老(水汲之伝) |
| 牡丹 | 石橋 |
| 木賊 | 木賊(とくさ) |
| 芭蕉 | 芭蕉 |
| おみなえし | 女郎花(おみなめし) |
| 夕顔 | 夕顔・半蔀(はじとみ) |
| 菊 | 菊(枕)慈童、猩々(菊の水) |
榊 |
野宮 |
| すすき | 井筒 |
| かえで | 六浦 |
| かずら | 定家(葛山)・葛城(天冠) |
| 虞美人草 | 項羽(虞美人草のいわれ) |
| 柳 | 遊行柳 |
| 紅葉 | 龍田、紅葉狩 |
| 杉葉 | 三輪・和布刈(めかり) |
| 椿 | 老椿(新作能) |
| その1・こんなにあるある花が出てくるお能の演目(フラワー能) |
お能には、花の精がシテとなって出てきたり、花を手に持ったり、冠に挿したり、作り物として飾られたりする。
今回は、そんなあるある話・・・フラワー能。
| 花 の 種 類 | 御 能 |
松 |
高砂、老松、羽衣。 |
| 竹笹 | 鳥追船、竹雪 |
| 笹枝(狂笹) | 隅田川、柏崎、百万 |
| 笹竹に文 | 花がたみ、高野物 |
| 梅 | 梅、箙、胡蝶、難波 |
| 若葉 | 求塚(芽吹いた薬草が若葉) |
| 桜 | 墨染桜、吉野天人、志賀、小塩 |
| 桃 | 西王母、東方朔 |
| 藤 |
藤 |
| 蕨 |
大原御幸 |
| 葵 |
加茂物狂 |
| 杜若 |
杜若 |
| 芍薬 |
養老(水汲之伝) |
| 牡丹 | 石橋 |
| 木賊 | 木賊(とくさ) |
| 芭蕉 | 芭蕉 |
| おみなえし | 女郎花(おみなめし) |
| 夕顔 | 夕顔・半蔀(はじとみ) |
| 菊 | 菊(枕)慈童、猩々(菊の水) |
| 榊 | 野宮 |
| すすき | 井筒 |
| かえで | 六浦 |
| かずら | 定家(葛山)・葛城(天冠) |
| 虞美人草 | 項羽(虞美人草のいわれ) |
| 柳 | 遊行柳 |
| 紅葉 | 龍田、紅葉狩 |
| 杉葉 | 三輪・和布刈(めかり) |
| 椿 | 老椿(新作能) |
| その2、こんなにあるあるお薦めのお能、見るならこれ |
| 見 る な ら ・・ | お 奨 め 能 は |
| 春見て華やかでお奨めなのが・・・・・ | 「草紙洗小町」「右近」「熊野」 |
| 秋見て華やかでお奨めなのが・・・・・ | 「紅葉狩」「江口」 |
| 人気曲でお奨めなのが・・・・・・・・・・ | 「羽衣」「高砂」 |
| 野外拝見でおお奨めなのが・・・・・・ | 「土蜘蛛」 |
| 義経と静御前が好きなら・・・・・・・・ | 「二人静」 |
| ちょっと怖いが見たい時は・・・・・・・・・ | 「鉄輪」 |
| ヒューマニズムの異色の能なら・・・・・ | 「藤戸」(源平、藤戸の合戦が素材) |
| 東京の人ならお奨めなのが・・・・・・・・・ | 「隅田川(角田川)」 |
| お稲荷さん氏子と商売繁盛でお奨めは・・ | 「小鍛冶」 |
| 特別演目、値段高めだがお奨めなのは・・ | 三老女:「姨(伯母)捨」「関寺小町」「檜垣」 |
| 復曲のお能なら・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 「鈿女(うずめ)」(金剛流) |
| 新作のお能なら・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 「道真(みちざね)」(菅公御神忌一千百年記念) |
| 運気を上げたい人にお奨めなのは・・・・ | 「翁」 |
(おまけ1)
|
| 【翁面について】 翁面は「天降(あまくだ)り面」ともいい、その大元は、天から降ってきたからという。それ故、翁面は神聖視され、 その面を著ける「翁」の演目自体も崇められた。また、見た者さえも淨められるという。 |
| 【お能の「絵馬」について】 時は元禄15年、忠臣蔵で有名な、松の廊下刃傷事件の時、勅使饗応の宴で上演されたお能の演目は、「絵馬」。芸州浅野家では以後、これを上演していない。 |
| 【昔は・・】 猿楽四座の長や権守が式三番を勤めた。現在の神事の中でも、金春権守代に御供物を下行(げぎょうー御祝儀に下げ渡すこと)する。装束は、淨衣・白袴の白式を著装。この能楽が重い神事である事を示す。春日神主の「始めす」の音声を受けて、笛が始まり開演する定めがある。古伝によると納めて退出の折、シテ翁は微音にて祈願文を唱えるという。「長久息災延命、今日の御祈祷なり。」との伝。 |
| その3、こんなにあるある春日大社で上演される芸能 |
| 神楽始式・・・・・ 1月3日 | 春日大社伝来の御巫(みかんこ…一般人神社の巫女)神楽秘曲を奉納 |
| 舞楽始式・・・・・1月15日 | 春日大社神職会、古楽保存会、南都楽所(なんとがくそ)が奉奏。 |
| 水谷狂言会(みずやきょうげん) ・・・・・・ 4月5日 |
午後、春日大社摂社例祭、神賑行事として、昭和30年に復興。春日禰宜座狂言会が奉納(大蔵流) |
| しゅし走り之儀の御能・・・ 5月11日 | 春日大宮にて上演。必ず「翁」を納める。 |
| 御社あがり之儀の御能 ・・・・・・・・・・5月12日 |
春日若宮にて上演。金春流が奉仕。橋掛りなどが逆勝手という珍しいたたずまいを今に残し、6本柱四方吹き抜けの拝舎で、若宮社を背に演舞する。酒樽(しゅそん)の下行など故実も多い。春日神主のほか興福寺からも衆徒が来社拝見する。 |
| 薪御能(たきぎおのう) ・・・・・・ 5月12日 |
春日大社藤原氏の氏寺、興福寺南大門跡、般若ノ芝にて上演。能楽四流派が揃い出演する特筆すべき御能で、能楽発祥の地ならではの格式を誇る。僧兵姿の衆徒5名も出仕検分する。 |
| 春日若宮おん祭りの神事芸能 ・・・・・・・・・ 12月17日 |
松の下式にて、猿楽座、田楽(でんがく)座、 細男(せいのお)座が儀礼的所作を奉納。猿楽座は「開口」、「弓矢立合」、「三笠風流」を金春流が納める。 元は、大和猿楽四座が出勤謹仕し、格式高い競演の場であった。 |
| 春日若宮おん祭りのお旅所祭にて神楽式 ・・・・・ 12月17日 |
翁の略式を奉納。三番三は、翁帰りのあとすぐ鈴ノ段を舞い、千歳は出ない。ひた面で奉仕している。これは、明治の初め、金春と金剛両大夫との協議により定められた行法。装束は白装を取り入れている。 |
春日若宮おん祭り、後宴能(ごえんのう) |
演目は各座で決める。 平成15年度は、西王母、末広がり、春日龍神。金春流が奉 |
| こんなにあるある・・・神社が元になっている言葉 |
| 今では普通に使われる言葉や地名も、その大元は、神社の神事や作法所作、 日本神話、神社音楽によるものがあります。 今回はそん~~~なあるある話!! 【画像は、春日大社1・2殿間に描かれた双口牽馬図の障壁絵馬】 |
 |
| 第1回目は、神社の神事(春日大社編、附・神事能)から |
| 時処位に応じる | 神事における、神様に対する神事奉仕者(天皇陛下を筆頭に神官など)のわきまえ方としての作法の基本 |
| げろう立ち | 神事奉仕者が座から退く時、下位の者から先に立ち上がる作法 |
| じょうろう立ち | 同様に、上位の者から先に立ち上がる作法 |
| 袖の下 | 今のイメージはあまり良くないが、元は、勅祭春日祭の神事中の作法。詳しく言えば、弁代と史代という役の人が書き物(見参)を受け渡しする作法で、右の袖下から渡す。 |
| 引き出物 | 元は、春日祭等における牽馬神事に由来する。神様に神の乗り物である生きた馬をさし上げる訳だが、現在は、絵馬の奉納ではなく、馬を連れて来て、神前でグルグルと牽(ひ)き回す所作(牽廻)に変わってきている |
| 絵馬 | 同上の生馬から順次、板に描いた馬の奉納に転じた為、生じた言葉。初見の絵馬は、春日大社本社間合いの障壁に描いてある3枚の大型の絵馬。絵柄は、馬寮官人が牽廻する飾り馬で、絵馬本来の姿を今に伝えている。ちなみに、乞雨祈願には、黒馬。止雨には白馬か赤馬を献じる慣わしと伝える |
| 結婚式の三三九度 | 祭の神事「饗膳」の三献之儀に由来する。この時は、第1献が清酒、第2献が濁酒、第3献が清酒の順となる。 春日祭では、お勅使一行に、宮司が盃を進め、権宮司が酒を盛る作法となっている |
| 高見の見物 | 春日おん祭りの松の下式で、春日神主と畏頭(かとう)姿(僧兵みたいな感じ)の頭屋児(とうやのちご)とが、松 のそばの高い場所の見所から奉納演舞を披見したことによる。 |
| 影向の松 | 同上の松に、春日の神様が降臨し、翁の姿で、万歳楽を舞われた故事に由来する。この松を芸能の神の依り代とする |
| 能舞台鏡板の松 | これが元で、今の能舞台の鏡板には、松の下式を模して、呪力ある春日の老松(樹種は黒松)を描きこむのである |
| 埒が明く(明かない) | 春日若宮おん祭りでの、「金春の埒明け」が元。お旅所へ猿楽四座の金春大夫が入る時に、柴の垣に結び付 けてある白紙を解くという神事作法に由来する。 |
| こんなにあるある「菅原道真公が出てくる演目」 |
さて、今回は、神社を舞台にした物の中でも、題材としては、一番多く語られている、
菅原道真公を主人公としている御能や謡曲の演目のあるある話。題材は、綾瀬天神(北野神社)の御祭神でもある菅原道真公(菅公・天神様)
| 御 能 | 種 別 | 備 考 |
| 老松 (おいまつ) | 真之脇能 | 大宰府天満宮が舞台 |
| 右近 (うこん) | 一番目脇能物 | 北野天満宮が舞台 |
| 道明寺(どうみょうじ) | 一番目脇能物 | |
| 藍染川(あいそめがわ) | 四・五番目物 | 大宰府天満宮が舞台 |
| 雷電 (らいでん) | 五番目切能物 | |
| 輪蔵 (りんぞう) | 五番目切能物 | 北野天満宮が舞台 |
| 菅丞相(かんしょうじょう) | 復曲一番目物 | 大阪天満宮「寄進御能(勧進能)」百五拾年記念で初演 |
| 道真 (みちざね) | 新作能 | 御神忌一千百年記念として、大宰府天満宮で初演 |
| 一夜天神(いちやてんじん) | 謡物 |
| 白髪 (はくはつ) | 謡物 |
【注意】「かんしょうじょう」の読みについて
じょうしょうが、普通の読み方ですが、お能は逆で、しょうじょうと読んでいます。唐松
| 落語でもあるある天神さまの出てくる噺 |
実は落語でもあるんですね。ただ落語ですからためになるとか、勉強になるような噺ではないんですね。(円)
| 落語の題名 | 内 容 |
| 質屋蔵(ひちやぐら) | 質に入れられた天神さまの掛け軸から、菅原公が出てきて嘆く。「ああ、またどうやら流されそうだ!」と言うのがオチ。下らないねえ。 |
| 狸賽(たぬさい) | 助けた狸が恩返しにやって来たので「これから博打をやるからサイコロになって言った目を出してくれ」と言って。5の目を教える時「梅鉢の紋だよ。分かるだろ?天神様だよ。勝負!」って開けると中で狸が、冠をかぶって釈を持ってた。これがオチ。やっぱり下らない。 |
| こんなにあるある「神社が舞台の御能の演目」 |
唐松家には、小面(こおもて、若い女性の面)など能面や神楽面など明治時代の物がいくつも残されている。また、一族の多くは金春流(狂言方・大蔵流)をたしなんだとい
う(現在は、観世流で舞う人がほとんど)。奈良の春日大社では、神職全員が「春日 禰宜座狂言会」(大蔵流)に入会するので、唐松宮司は親から、大社での修行を指示されたそうだ。
短い舞は、観世など能の一部としての物は、仕舞というが、狂言方では、 短い舞を小舞(こまい)と呼ぶという違いがあるのだそうです。奈良修行中には、現宗家の二十四世彌右衛門(当時は彌太郎先生)師に師事したそうだ。
禰宜座で最初に習う曲目は、一様に「泰山府君」。小舞の初舞台は「盃」。宗家は大体「福の神」を舞 われるのが常だそうです。一般的には多くの謡で最初に稽古する入門曲は「鶴亀」
だそうですが、大体の節回しが入っている「猩々」で始める所もあるとか。
| 唐松氏に御能で一番好きなものはと聞いたら人気曲ですが「羽衣」。シテが言う 「いや疑ひは人間にあり、天に偽りなきものを」、これに答えて、「あら恥ずかしや
さらばとて」とワキもすぐに反省する場面が良いからだそうです。 尚、御能では上演回数も多い、稲荷神の霊験を説いた「小鍛冶」という曲目がある。 唐松家は、お稲荷さんの社家なので、その小鍛冶の名場面、小狐が相槌となって、名剣 小狐丸を打っているシーンの彫金の額が、昔からあって、現在は応接室に掲げられてい るとの事。 さて御能は、神社を舞台にして、その祭神の神徳を称え、神社の縁起を語ったものが種々にある。今回は、そんなあるある話である。 【画像:稲荷神の霊験を説いた「小鍛冶」】 |
 |
| 神社が舞台の御能の演目 |
【奈良県の神社には】
| 舞台になっている神社 | 能の演目 |
| 伊勢神宮 | 内外詣、御裳濯川、絵馬、大六天 |
| 熱田神宮 | 草薙、源太夫 |
| 出雲大社 | 大社、初雪 |
| 春日大社 | 春日龍神、野守 |
| 春日・采女神社 | 采女 |
| 石上神宮 | 布留 |
| 大神神社 | 三輪 |
| 高鴨神社 | 代主 (内容から言うと、葛城一言主神社) |
| 吉野山勝手神社 | 二人静 |
| 龍田大社 | 龍田、逆矛 |
【京都府の神社には】
| 舞台になっている神社 | 能の演目 |
| 伏見稲荷大社 | 小鍛冶 伏見・金札宮 金札 |
| 賀茂別雷神社(上賀茂) | 賀茂、矢卓鴨 |
| 賀茂御祖神社(下鴨) | 賀茂物狂、班女、水無月祓 |
| 北野天満宮 | 右近、輪蔵 |
| 石清水八幡宮 | 弓八幡、放生川、女郎花采女 |
| 大原野神社 | 小塩 |
| 松尾大社 | 松尾 |
| 野宮神社 | 野宮 |
| 貴船神社 | 鉄輪 |
【大阪府の神社では】
| 舞台になっている神社 | 能の演目 |
| 住吉大社 | 住吉詣、高砂、雨月 |
| 蟻通神社 | 蟻通 |
| 大阪天満宮 | 菅丞相(復曲、「寄進御能(勧進能)」150年記念) |
【滋賀県の神社では】
| 舞台になっている神社 | 能の演目 |
| 竹生島神社 | 竹生島 |
| 白鬚神社 | 白鬚 |
| 大阪天満宮 | 菅丞相(復曲、「寄進御能(勧進能)」150年記念) |
【そのほかの神社では】
| 舞台になっている神社 | 能の演目 |
| 江島神社(神奈川県) | 江島、鱗形 |
| 気多大社(石川県) | 鵜祭 |
| 鵜戸神宮(九州) | 鵜羽 |
| 筥崎宮(九州) | 箱崎(復曲) |
| 大宰府天満宮 | 老松、藍染川、道真(新作能、御神忌一千百年記念) |
| 和布刈神社 | 和布刈 |
| 小謡(こうたい) 3題 「鶴亀」謡曲 庭の砂(いさご)ハ金銀の(繰) 珠を連ねて敷妙乃 五百重(いおえ)の錦や瑠璃の樞(とぼそ) しゃこの行桁瑪瑙の階(はし) 池の汀乃鶴亀ハ 蓬莱山も外(よそ)ならず 君乃恵みぞありがたき(繰) 「泰山府君」謡曲(美しい小謡と評判) 哀れ一枝を 花の袖に手(た)折りて 月をもともに詠免(ながめ)ばやの 望みは残れり この春の 望み残れり 「盃」謡曲 盃に向へば いろも猶赤くして 千と世の命を 延ぶる酒と きくものを きこし召せや きこし召せ 寿命久しかるべし |
| こんなにあるある「綾瀬」のつく名前 |
(調査、研究、資料などなど・・・唐松氏より)
| 綾瀬川とは? |
綾瀬川とは、江戸時代よ蛇行を繰り返す暴れ川。桶川市小針領家を起点に長さ約48kmの一級河川で下流で旧利根川(現、中川)に合流した。綾瀬1・2丁目には、今でも古(ふる)
隅田川が流れており、元隅田橋・白鷺橋・鵜乃森橋・北野橋など古橋が今に残る。かっての綾瀬川は、秋の鯉が名産品でねぶの花や薮蚊の多い所としても有名。
舟運は、上りも下りも大いに盛んで下肥も資源として帆掛け舟(高瀬舟)で運搬した。トラック輸送が始まる、昭和30年代までは、川船による水上交通が物資運搬の主力でした。
| 【昔は隅田川の一部だった・・】 古歌においては、隅(角)田川の一部分(上流)として詠まれたものも多いので、 古歌はその意味合いから、今の綾瀬川なのか隅田川なのかを判断しないといけない。 【最も古いと思われる「綾瀬川」の歴史的資料】 「川あるによりて、『何川だ』と問いせるに、大河と申すといふに、壱人は『あやし川』といふ、壱人は『あやせ川』とも答ふ。」云々・・・・『結城使行』(元禄16)水野長富より |
| こんなにあるある綾瀬川の歌 |
| 五月雨になみたもそうやあやせ川 あやなく物を思う頃哉 正岡子規 |
| 白き帆の風をはらみて来る時 綾瀬の川はゆふべなりけり 金子薫園 |
| あやせ川ねぶの花ちるしののめに 瓜つむ小舟波にこぐ見ゆ 小林歌城 |
| 角田川あや瀬の瀬波しるけれど あやなく花の色くれないに 安藤野雁 |
| ほの見へしうすくれなゐの一むらは 綾瀬の岸のねぶの花かも 加藤千蔭 |
| あやせ川水のよどみに所得て むれにむれたるあじのむら鳥 関 智雄 |
| よしきりや列をはなれて小さき帆の 綾瀬に折れし昼下がりかな 石榑千亦 |
| ゆく水の波織かくるあやせ川 かわの名しるし見るゆ錦藻 加藤敬豊 |
| 曲がりこむ 藪の綾瀬や 行蛍 建部巣兆 |
| 綾瀬川かわ瀬を渡るきよ風に 鳥の飛び立つその音のあや 唐松宮司 |
| 【参考句歌】 肥舟の 霞んでのぼる 隅田川 正岡子規 名月や 薮蚊だらけの 角田川 小林一茶 今宵また誰が宿からむ庵崎の すみだ河原に秋の月影 順徳院 (注)庵崎とは、綾瀬川と千住川の合流地点にできた出洲。牛田村の堤外地。今の墨田区堤通2、綾瀬橋付近。 |
| 綾瀬地区限定版あるあるシリーズその1 こんなにあるある「綾瀬」のつく名前 |
| 東綾瀬中学校 | 足立区綾瀬3丁目 |
| 東綾瀬小学校 | 足立区東綾瀬2丁目 |
| 綾瀬小学校 | 足立区綾瀬3丁目 |
| 南綾瀬小学校 | 葛飾区堀切6丁目1-1 |
| 綾瀬駅 | 千代田線綾瀬駅(綾瀬3丁目) |
| 北綾瀬駅 | 綾瀬より引き込み線(谷中2丁目) |
| 綾瀬新橋 | 綾瀬6丁目 |
| 綾瀬橋 | 千住曙町(隅田川合流口) |
| 綾瀬稲荷神社 | 当社・足立区綾瀬4-9-9 |
| 綾瀬神社 | 足立区綾瀬1-34-26 |
| 綾瀬北野神社 | 足立区綾瀬2-23-14 |
| 綾瀬 | 綾瀬1~7丁目 |
| 東綾瀬 | 東綾瀬1~3丁目 |
| 西綾瀬 | 西綾瀬1~4丁目 |
| 綾瀬自治会 | |
| 綾瀬東自治会 | |
| 綾瀬西自治会 | |
| 西綾瀬自治会 | |
| 東綾瀬自治会 |
| 「綾瀬」、「あやせ」、「アヤセ」と付いている病院名 | 計14 |
| 新加平橋、みどり歩道橋、綾瀬新橋、五兵衛橋、新五兵衛橋、伊藤谷橋、水戸橋、新水戸橋、堀切橋、墨田水門、綾瀬橋。 |
計11 |
| こんなにあるある三社パートⅡ |
| これが日本三大船祭り | |
| 津島天王祭 | 愛知県津島市・津島神社 |
| 天満天神祭 | 大阪市・大阪天満宮 |
| 厳島管弦祭 | 広島県・厳島神社 |
| これが日本三大神鏡(国宝指定) | |
| 珍宝鏡 | 奈良市・正倉院御物唐代4面 |
| 御神鏡 | 千葉県・香取神宮・海獣葡萄 |
| 御神鏡 | 愛媛県・大山祇神社 |
| これが日本三大八幡宮 | |
| 宇佐神宮 |
大分県 |
| 石清水八幡宮 | 京都 |
| 鶴岡八幡宮 | 神奈川県 |
| これが三大有名(別称がある)神社 | |
| 京都宮津・籠(この)神社 |
「元伊勢」(吉佐宮・よさのみや) |
| 長崎の諏訪神社 | 「鎮西の大社」 |
| 愛媛・大山祇神社 | 「日本総鎮守」 |
| これが日本三名山 | |
| 富士山 | |
| 立山(たてやま) | |
| 白山(はくさん) |
| これが白山3峰(はくさん さんぽう) | |
| 御前峰(ごぜんがみね)富士山 | |
| 大汝峰(おおなんじみね) | |
| 別山(べっさん) |
| こんなにあるある・・お稲荷さん! |
| こんなにある国神社調査によると(端数はカット) | |
| 全国の神社は | 12万社 |
| 神社本庁の所管神社は | 8万社 |
| 東京都神社庁の所管神社は | 1400社 |
| お稲荷さんは伏見稲荷神社を御本社に全部で | 32000社 |
| 天神さんは大宰府天満宮を御本社に全部で | 10400社 |
| 浅間さんは富士山浅間神社を御本社に全部で | 1300社 |
| そのうち、富士山の周囲だけで | 150社 |
| 氷川さんは、埼玉氷川神社を御本社に全部で | 280社 |
| お伊勢さんは伊勢神宮を御本社に全部で | 18000社 |
| 八幡さんは、宇佐神宮を御本社に全部で | 25000社 |
| 春日さんは、春日大社を御本社に全部で | 1300社 |
| 宗像さんは宗像大社を御本社に全部で | 9000社 |
| お諏訪さんは諏訪大社を御本社に全部で | 5000社 |
| 日吉さんは日吉大社を御本社に全部で | 3800社 |
| 津島さんは愛知津島神社を御本社に全部で | 3000社 |
| 八坂さんは京都八坂神社を御本社に全部で | 2600社 |
| 熱田さんは、熱田神宮を御本社に全部で | 2000社 |
| 松尾さんは松尾大社を御本社に全部で | 1100社 |
| 愛宕さんは京都愛宕神社を御本社に全部で | 800社 |
| 金刀比羅さんは金刀比羅宮を御本社に全部で | 680社 |
| 護国神社は靖国神社を御本社に全部で | 42社 |
| 熊野さんは熊野3社を御本社に全部で | 3000社 |
| お多賀さんは多賀大社を御本社に全部で | 230社 |
| 鹿島さんは鹿島神宮を御本社に全部で | 910社 |
| 香取さんは香取神宮を御本社に全部で | 470社 |
| 東照宮は久能山東照宮を御本社に全部で | 100社 |
| 乃木神社は東京乃木神社を御本社に全部で | 5社 |
| こんなにある変幻自在の異名 |
| 芸 名 | 三遊亭 円丈 |
| 本名 | 大角 弘 |
| 女房から | あなた |
| 子供から | お父さん |
| お弟子さんから | 師匠 |
| 狛犬仲間から | 先生! |
| 真打ち前の名前 | ぬう生 |
| 20センチ位 | ワカシ |
| 40センチ位 | イナダ |
| 60センチ以上 | ワラサ |
| 90センチ以上 | ブリ(鰤) |
| スルメ | 当たり目 |
| かみそり | 当たりがね |
| 豆腐 | 豆富 |
| 台所の布巾 | 富金運 |
| カツ丼 | 勝登運 |
| ゴミ箱 | 護美箱 |
| 死 | 直る |
| 血 | 赤汗 |
| 仏 | 中子・なかご |
| トイレお借りします | よそよそ |
| お米 | およね |
| お餅 | おかちん |
| うどん | つるつる |
| お尻 | おいど |
| 大穴牟遅神(おほなむち の かみ) |
| 葦原色許男命(あしはらしこを の みこと) |
| 八千矛神(やちほこ の かみ) |
| 宇都志国玉神(うつしくにたま の かみ) |
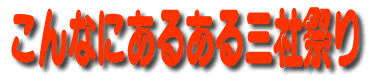 |
目下綾瀬稲荷神社、北野天神、綾瀬神社の三社で綾瀬三社祭りを企画中。そこで今回は全国にこんなにある。
三社祭りを紹介しよう。ありすぎて驚かないでちょうだい!!今回のアデイアとデータ提供は、宮司さんの唐松氏。
| まず全国的な三社と祭り |
東京では三社と言えば、浅草三社神社だが、しかし神社界で三社と言えば・・、
そして日本3大祭りと言えば、このようになるんです。
| 神社界の三社とは | 「伊勢神宮(三重) | 石清水八幡宮(京都) | 春日大社(奈良) |
| 日本三大祭り | 石清水祭 | 葵祭(京都・上下の鴨神社) | 春日祭 |
| これが日本各地の三社祭り |
もう日本全国の三社祭りといえば、こ~~~んなにあるある。
| 東北の三社祭 (別名:相馬馬追祭り) |
福島県の太田神社 | 中村神社 | 小高神社 |
| 東北三大夏祭り |
ねぶた(青森市) | 竿燈(秋田) | 七夕まつり(仙台) |
| 長崎三大行事 | 諏訪神社(おくんち) | 森崎神社(ペーロン) | 住吉神社(凧上げ【はたあげ】) |
| 愛媛三社祭(西条祭り) | 岩岡神社 | 伊曾乃神社 | 飯積神社 |
| 和歌山熊野三社 | 熊野本宮大社 | 熊野速玉大社(新宮) | 熊野那智大社 |
| 山形の出羽三山神社は | 月山神社 | 出羽神社 | 湯殿山神社 |
| 埼玉秩父の三社は | 秩父神社(知々夫) | 宝登山神社(火止山) | 三峯神社(参美祢) |
| 福岡の宗像(むなかた)三社 | 沖津宮(おきつみや) | 中津宮(なか) | 辺津宮(へ) |
| 京都三大祭り | 葵祭 | 祇園祭(八坂神社) | 時代祭(平安神宮) |
| 東京三大祭り | 神田祭(神田明神) | 浅草三社祭 | 赤坂山王祭(天下祭、日枝神社) |
| おまけ・・その他のニ大、三大 |
そのほか、2大なんとか、3大なんとかを上げてみると・・・いやあ、いっぱいあるある!!
| 江戸時代の二大祭は | 天下祭 | 神田祭(江戸城に隔年で参入) | |
| 江戸時代の 下町庶民の二大祭 |
浅草三社祭 | 深川祭(八幡祭、富岡八幡宮) | |
| 江戸の三富 (富くじ、宝くじ) |
湯島天神 | 谷中天王寺 | 目黒不動 |
| 江戸の三大火事 | 振袖火事(本妙寺) | 行人坂火事(大円寺) | 芝車町火事 |
| 台東三大市 | 入谷朝顔市(7月) | 浅草ほおずき市(7月) | 浅草羽子板市(12月) |
| 日本三大火祭り | 那智(熊野那智大社) | 吉田(富士浅間神社) | 鞍馬(由岐神社) |
| 日本三大曳山は | 秩父夜祭(秩父神社) | 祗園祭の山鉾 | 高山祭(日枝・桜山八幡) |
| 日本三大稲荷は | 伏見稲荷(京都) | 祐徳稲荷(佐賀) | 笠間稲荷(茨城) |
| 日本三大弁天は | 厳島神社(広島) | 竹生島神社(滋賀) | 江島神社(神奈川) |
| 日本三大霊場は | 比叡山(京都) | 高野山(和歌山) | 恐山(青森) |
| 日本三大囃子は | 飾山囃子(おやま・秋田、神明社) | 祗園囃子 | 馬鹿囃子(東京) |
| 日本三大名園は | 、偕楽園(水戸) | 後楽園(岡山) | 兼六園(金沢) |
| 日本三大河川 | 利根川(坂東太郎) | 筑後川(筑紫二郎) | 吉野川(四国三郎) |
| 日本三景は | 安芸の宮島(広島) | 陸前の松島(宮城) | 丹後の天橋立(京都) |
| 日本三大金魚養殖地は | 一之江(東京) | 弥富(愛知) | 郡山(奈良) |
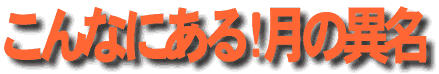 |
しかし日本って言葉の豊かな国だね。1月の異名がなんと14もある。正直驚いた。そこで1年を12ヶ月の異名を載せることにした。とりあえず今回は1月~4月のまでの4ヶ月分をUPした。 三遊亭 円 丈
【1月】
| 数 | 異名 | 読 み |
| 1 | 孟春 | もうしゅん |
|
2 |
元月 | がんげつ |
|
3 |
早緑月 | さみどりつき |
| 4 | 正月 | しょうがつ |
| 5 | 年始月 | としはづき |
| 6 | 太郎月 | たいろうげつ |
| 7 | 祝月 | いわいつき |
| 8 | 陽春 | ようしゅん |
| 9 | 初春月 | はつはるづ き |
| 10 | 霞初月 | かすみそめ づき |
| 11 | 初空月 | はつそらづき |
| 12 | 子の日月 | ねのひつき |
| 13 | 十三月 | じゅうさんづき |
| 14 | 年端月 | としはづき |
【一言コメント】
落語の小話に「一年は十三ヶ月だと..」と言うのがあるけど。十三月なんて言い方があったんだね。それから「孟春」と言うのは良く江戸期の狛犬の碑文にあるけど3月あたりかと思っていた。正月のことだったんだ!びっくし!!
【2月】
| 数 | 異名 | 読 み |
| 1 | 如月 | きさらぎ |
|
2 |
令月 | れいげつ |
|
3 |
麗月 | れいげつ |
| 4 | 仲春 | ちゅうしゅん |
| 5 | 夾鐘 | きょうしょう |
| 6 | 梅つ月 | うめつづき |
| 7 | 大壮月 | だいそうづき |
| 8 | 梅見月 | うめみづき |
| 9 | 木芽月 | このめづき |
| 10 | 雪消月 | ゆきぎえづき |
| 11 | 小草生月 |
おぐさおいづき |
【一言コメント】
「仲春」もどっかで聞いたことがあるような気がするが、2月だったとは?知らなんだ。
【3月】
| 数 | 異名 | 読 み |
| 1 | 弥生 |
やよい |
|
2 |
桜月 | おうげつ |
|
3 |
嘉月 | かげつ |
| 4 | 季春 | きしゅん |
| 5 | 桃月 | ももづき |
| 6 | 雛月 | ひいなづき |
| 7 | 蚕月 | さん げつ |
| 8 | 禊月 | けいげつ |
| 9 | 竹の秋 | たけのあき |
| 10 | 夢見月 | ゆめみづき |
| 11 | 春惜月 | はるおしみづき |
| 12 | 花見月 | はなみづき |
| 13 | 染色月 | しめい ろづき |
| 14 | 早花咲月 | さはなさづき |
【一言コメント】
「竹の秋」で3月!なんでだろう?3月、竹の秋。う~~ん。蚕月で3月。蛾になるのかね。もうクイズだね。
【4月】
| 数 | 異名 | 読 み |
| 1 | 卯月 | うづき |
|
2 |
乾月 | かんげつ |
|
3 |
陰月 | いんげつ |
| 4 | 鳥月 | とりづき |
| 5 | 麦秋月 | ばくしゅうげつ |
| 6 | 卯花月 | うのはなづき |
| 7 | 清和月 | せいわづき |
| 8 | 夏初月 | なつはづき |
| 9 | 花残月 | はなのこりづき |
| 10 | 鳥来月 | とりくづき |
| 11 | 鳥待月 | とりまちづき |
| 12 | 花名残月 | は ななごりづき |
| 13 | 得鳥羽月 | えとばづき |
| 14 | 木葉取月 | このはとりづき |
【一言コメント】
4月は鳥が来たり、鳥が待ったり、するのかね。いやあ、分からん。
◎近々、5月~8月までをUPする。尚、この異名は金園社「日本の年中行事」弓削悟著(2330円)を参考にさせて頂いた。